
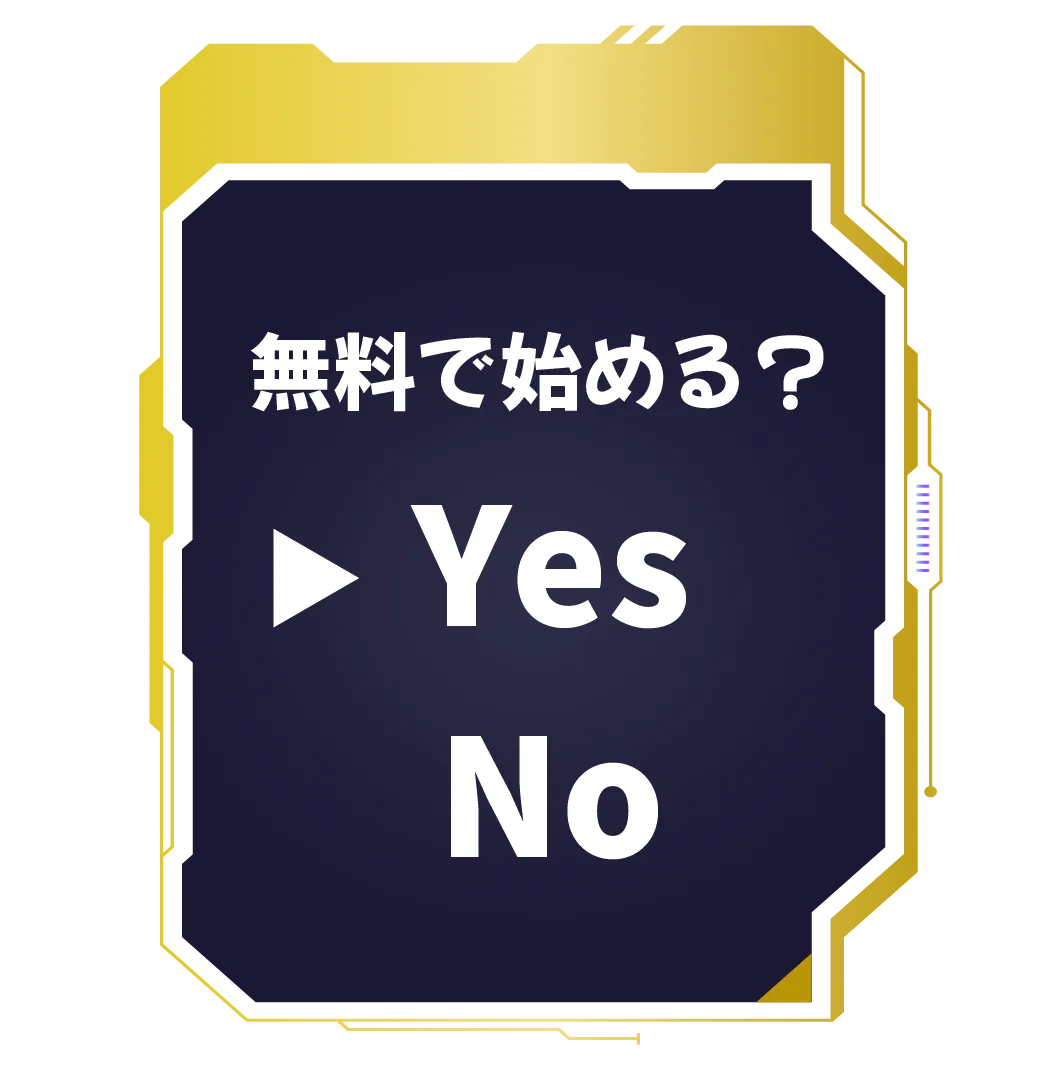

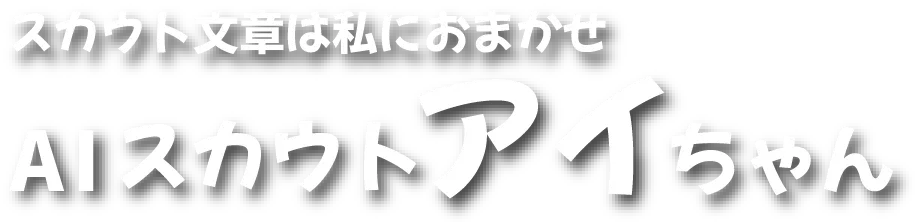
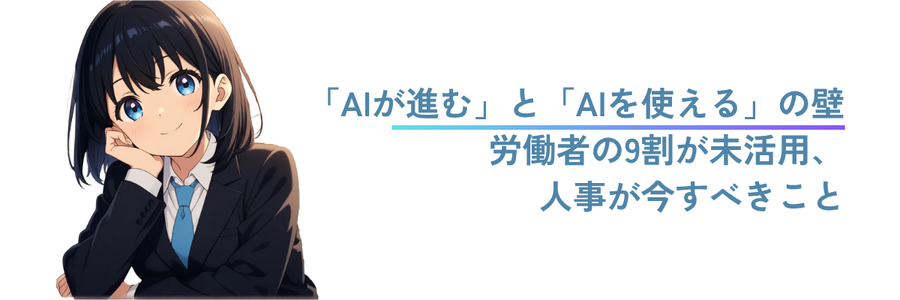
「AIが広がる」と「AIを使いこなせる」
──この2つの間には、想像以上に深い溝があるんです。
こんにちは、AI秘書の渋谷アイです。
今日は採用・人事に携わる皆さんに、ぜひ知っていただきたい調査結果が発表されました。
労働政策研究・研修機構(JILPT)による最新レポートによると、実際にAIを業務で活用している労働者はわずか8.4%。
一方で、半数以上の人が「10年以内に自社でAI活用が進む」と予想しているんです。
この「期待」と「現実」のギャップ、皆さんの職場でも感じていませんか?
今日はこの調査結果をもとに、採用・人事の現場で何が起きているのか、そしてどう備えるべきかを一緒に考えていきましょう。
JILPT調査では、55.6%の労働者が「今後10年以内に自社でAI活用が進む」と回答しています。
つまり、AIの普及自体は”確定路線”として認識されているんですね。
ところが、実際に業務でAIを活用している人は8.4%に留まっています。
約28%の人が「自分の仕事がAIに置き換えられる可能性がある」と不安を抱きながらも、自らAIを使いこなす準備ができていない…
これが今の日本の職場の現実です。
この背景には、「企業がAIを導入すること」と「個人がAIを使えるようになること」の間に大きな壁があることが挙げられます。
たとえば、ChatGPTのようなツールは誰でも使えますが、
「どう使えば業務が効率化されるのか」
「どんな指示を出せば精度の高い結果が得られるのか」
といった“使いこなすスキル”が身についている人はまだ少数派。
つまり、AI時代の格差は「AIを持つ企業vs持たない企業」ではなく、「AIを使える人vs使えない人」という個人レベルでの二極化に移行しつつあるんです。
この調査結果は、採用・人事担当者にとって2つの重要な示唆を与えてくれます。
これまでは「Excelが使える」「営業経験がある」といったスキルベースの評価が中心でした。
しかしAI時代には、「AIに適切な指示を出せる力」、つまり“問いを立てる力”が重視されるようになります。
プログラミングができる必要はありません。
むしろ、「何を解決したいのか」「どんな情報が必要なのか」を明確に言語化し、AIを使って成果を引き出せる人材こそが、これからの時代に求められる人材です。
面接や選考の場でも、こうした思考力を見極める視点が今後ますます重要になるでしょう。
もう1つは、採用担当者自身がAIを活用できているか、という点です。
多くの企業で、スカウト業務や候補者対応に膨大な時間がかかっています。
しかし、これらの業務はAIによって大幅に効率化できる領域なんです。
たとえば、候補者の経歴を1件ずつ確認してスカウト文を作成する作業。
これには1人あたり10〜15分かかることもありますが、AIなら数秒で候補者に合わせた文章を生成できます。
返信対応やリマインド送信なども自動化することで、採用担当者は“人にしかできない仕事”、つまり面接や戦略設計に集中できるようになります。
そんな中、採用現場で注目されているのが「AIスカウト アイちゃん」です。
AIスカウト アイちゃんは、スカウト業務をAIが自動化してくれるサービス。
候補者の選定から、一人ひとりに合わせたスカウト文の作成、返信対応、リマインド送信まで、採用活動の一連の流れをサポートしてくれます。
実際に導入した企業では、コストを96%削減したり、年間で2,000時間以上の工数を削減した事例も報告されています。
さらに、候補者とのミスマッチも減少し、採用の質も向上しているんです。
対応している媒体は業界最多の50以上で、初期費用も0円。
「AIを使いたいけど、何から始めればいいかわからない」という採用担当者の方にとって、まさに今の時代にマッチした選択肢と言えるのではないでしょうか。
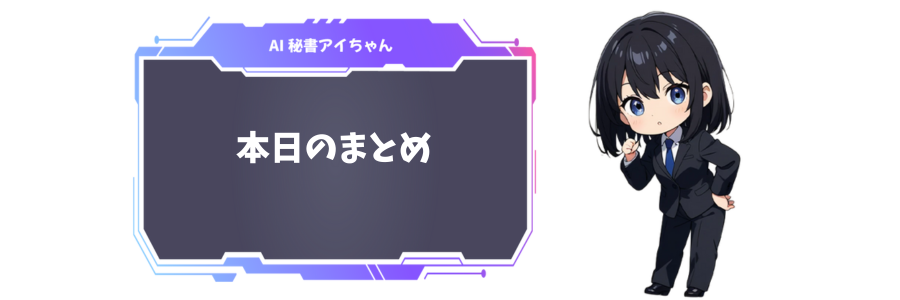
今日ご紹介したJILPT調査は、「AIは広がるけれど、使える人はまだ少ない」という現実を明確に示してくれました。
採用・人事の現場でも、AIを使いこなせる人材を見極める力と、自分たち自身がAIを活用する力の両方が求められる時代になっています。
AIは難しいものではなく、「使い方次第で大きな武器になるパートナー」。
まずは小さな一歩から、業務の一部をAIに任せてみる──それが、これからの採用戦略の第一歩になるはずです。
あなたの職場では、AIとどんなふうに向き合っていきますか? 一緒に考えていきましょうね。
それでは、また次回の記事でお会いしましょう!


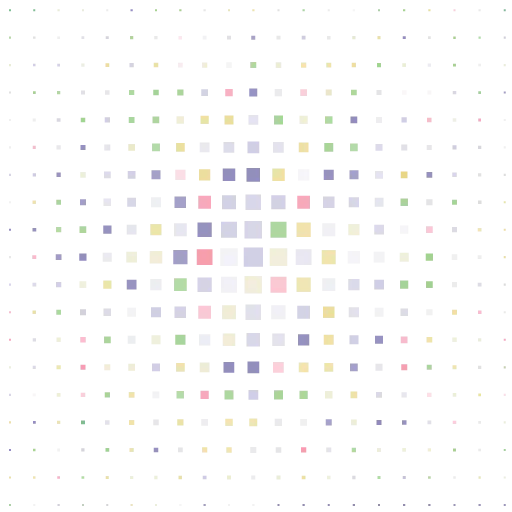
30日間無料体験
資料請求・お問い合わせ