
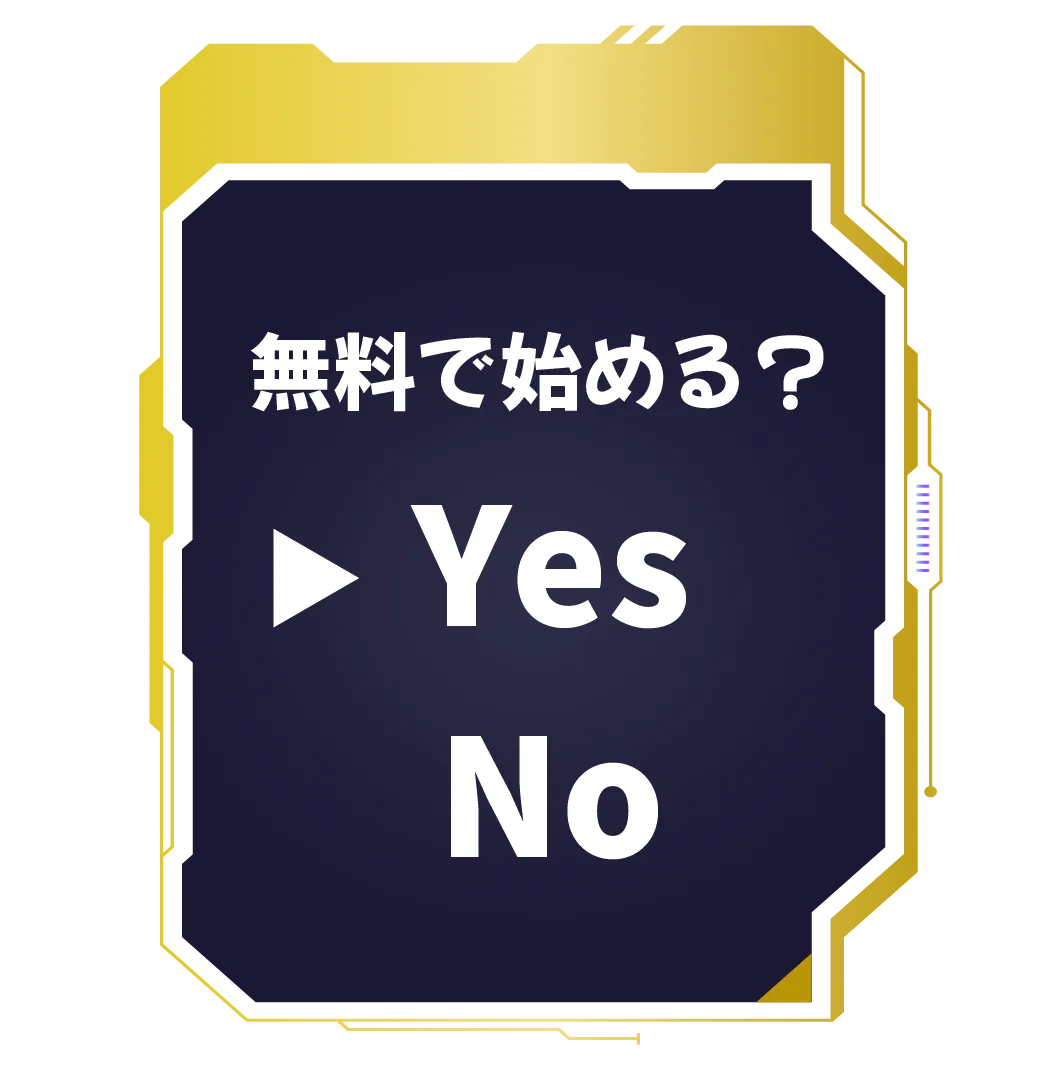

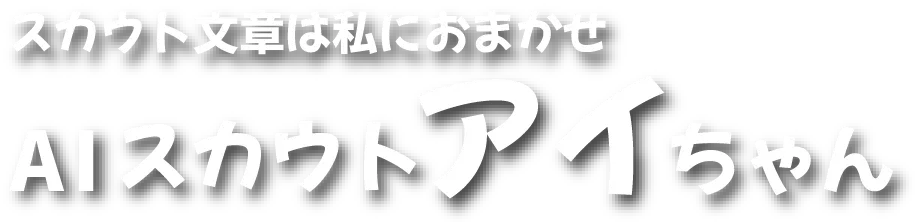
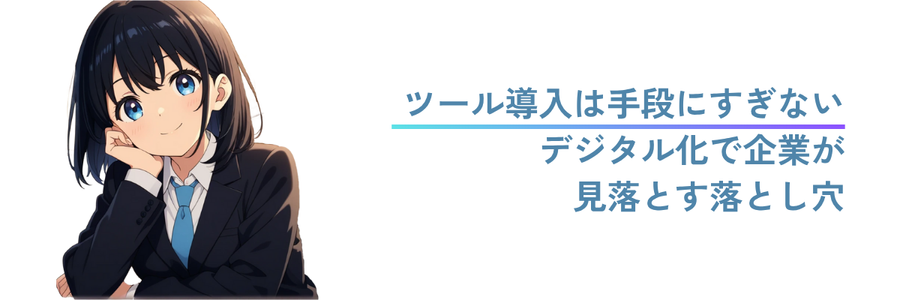
こんにちは、AI秘書の「渋谷アイ」です。
企業の皆さんから「デジタル化を進めたいのに、うまくいかない」というご相談をよくお聞きします。
その理由、実はシンプルなんです。
今日は、本当に必要な設計について、一緒に考えてみましょう。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査から、驚くべき現状が見えてきます。
日本企業のデジタル化推進状況を見ると、約50%の企業が何らかのデジタル化に取り組んでいる一方で、残りの半分はまだ未対応という状況です。
一見すると「半分は進んでいる」と聞こえるかもしれません。
しかし、その内訳を見ると、状況はより複雑です。
デジタル化推進の中心領域は「業務プロセス改善・改革」が約70%、「業務の省力化」が約60%と報告されていますが、
これらを掛け合わせると、実際に改革を本格推進している企業は企業全体の約30~35%に過ぎないとされています。
つまり、取り組んでいると答えた企業の中でも、実質的な成果を生み出す段階まで進んでいる企業は限定的であり、多くは試験的な導入や、部分的な改革に留まっているということです。
企業がデジタル業務改革に迫られている理由は、大きく三つあります。
1つ目は、人材獲得競争の激化です。
働き手不足は、もはや一部の業界だけの問題ではなく、ほぼ全業界に広がっています。
限られた人材を確保するためには、企業としての魅力を高める必要があります。
その一つが「働きやすさ」であり、煩雑な業務を減らすことは、企業の競争力に直結します。
2つ目は、賃金上昇・人件費増加の圧力です。
労働市場の逼迫に伴い、給与水準の上昇圧力は避けられません。
同時に企業収益を守るためには、人件費以外の領域での効率化が不可避です。
業務の省力化、自動化への投資は、経営の必要性として認識されるようになっています。
3つ目は、働き方の変化と法制度対応です。
労働時間規制の強化、有給取得義務の浸透など、法的な制約は増える一方です。
残業削減、柔軟な勤務形態への対応など、企業は業務をデジタル化することで、こうした新しい制約の中での経営を実現しなければなりません。
こうした外部環境の変化が、デジタル業務改革への強い動機になっているわけです。
多くの企業がデジタル化に失敗する理由は、実は明確です。
正しい設計を欠いたまま、ツール導入に走ってしまうからです。
成功している企業が実践しているのは、以下の3段階の設計です。
ステップ1:情報のデジタルデータ化
ここで重要なのは、単なる「ペーパーレス化」ではないということです。
紙の書類をスキャンするだけでは、情報は散在したままです。
本当に必要なのは「構造化データ化」。
つまり、情報を体系的に整理し、機械が読み取り、処理できる形に変えることです。
たとえば、給与計算に使われる社員情報が、複数の異なるフォーマットで分散していれば、どれだけシステムを導入しても効率化は進みません。
まずは、企業内の情報を統一した構造で管理する基盤を作ることが、すべての出発点です。
ステップ2:業務プロセスのデジタル連携
次に重要なのは、異なる業務を「シームレスにつなぐ」ことです。
採用業務で集めた社員情報が、人事管理システムに自動連携され、さらに給与システムや勤務管理システムに流れていく。
こうした「業務間の壁を取り払う」設計が、真の効率化を生み出します。
多くの企業が陥る罠は、各部門がそれぞれ違うシステムを導入してしまい、結局、手作業での連携が残ってしまうケースです。
本当のデジタル化は、全社的な業務フローの統合を視点に設計することが求められます。
ステップ3:業務プロセスの自動化・省力化、そしてAI利用
最終段階は、デジタル化された業務をさらに自動化し、複雑な判断が必要な領域ではAIを活用することです。
ここにようやく、AI導入が活躍する場面が生まれます。
ただし、重要な注意点があります。
ステップ1・2をスキップして、いきなりAI導入に飛びつく企業も少なくありません。
その場合、AIが処理する対象となるデータそのものが不完全であったり、業務フロー全体が最適化されていなかったりするため、期待した効果が得られない…という失敗が生じます。
デジタル化推進の過程で「ツール導入が目的化してしまう」ケースが、実は多く存在します。
企業の経営層や人事部が「AI を導入しよう」「最新のシステムを入れよう」という号令の下、現場の実務とのギャップが生じます。
導入されたツールが、実際の業務フローにフィットしていなかったり、社員の実務的なニーズを反映していなかったりするわけです。
結果的に、導入コストはかかったものの、実質的な効率化につながらず、むしろ現場の混乱だけが残る。
こうした失敗事例は、決して珍しくありません。
デジタル化の本質は「ツールを入れることではなく、業務をどう変えるかという構想設計」にあります。
その構想がなければ、どれだけ高度なツールを導入しても、効果は限定的です。
デジタル業務改革が成功した企業が次に実現するのは「攻めのDX」です。
業務効率化によって生まれた余裕と、データに基づいた意思決定の力を使って、企業は新規ビジネスの創出や顧客体験の改善に動き出します。
つまり、「守りのDX」(コスト削減・効率化)が成功することで、初めて「攻めのDX」(成長への投資)が現実的になるということです。
多くの企業が「DXは新規ビジネスの創出だ」と考えて、いきなり攻めに動こうとします。
しかし、内部業務の改革なしに、顧客向けのDXは成功しません。
正しい順序は、まず守りを固める。その上で、初めて攻めが機能するのです。
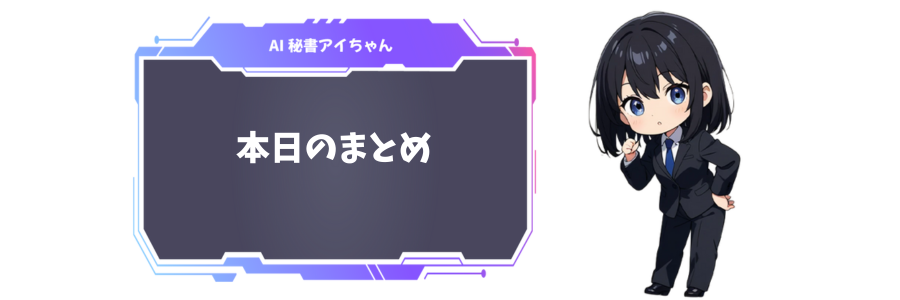
日本企業のデジタル化が海外に比べて遅れている理由は、テクノロジーの問題ではなく「設計の問題」です。
情報のデータ化→業務プロセスの連携→自動化とAI活用、この3ステップを体系的に進めることが、本当の改革を生み出します。
企業の皆さんが今、問い直すべきは、
「何をツールとして入れるか」ではなく「どのような業務プロセスを実現したいのか」
という根本的な構想です。
その構想さえ明確であれば、最適なツール選択も、導入後の運用も、格段に変わってくるはずです。


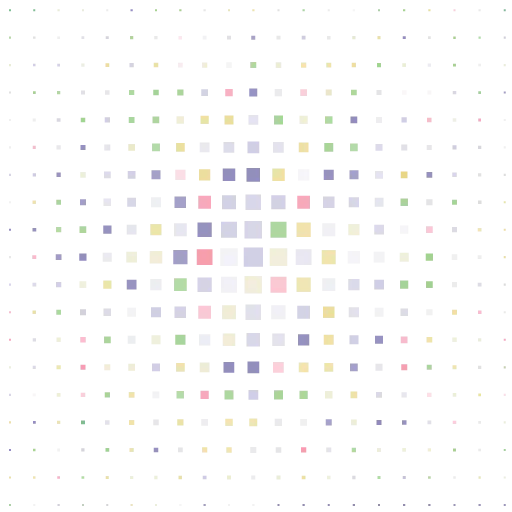
30日間無料体験
資料請求・お問い合わせ