
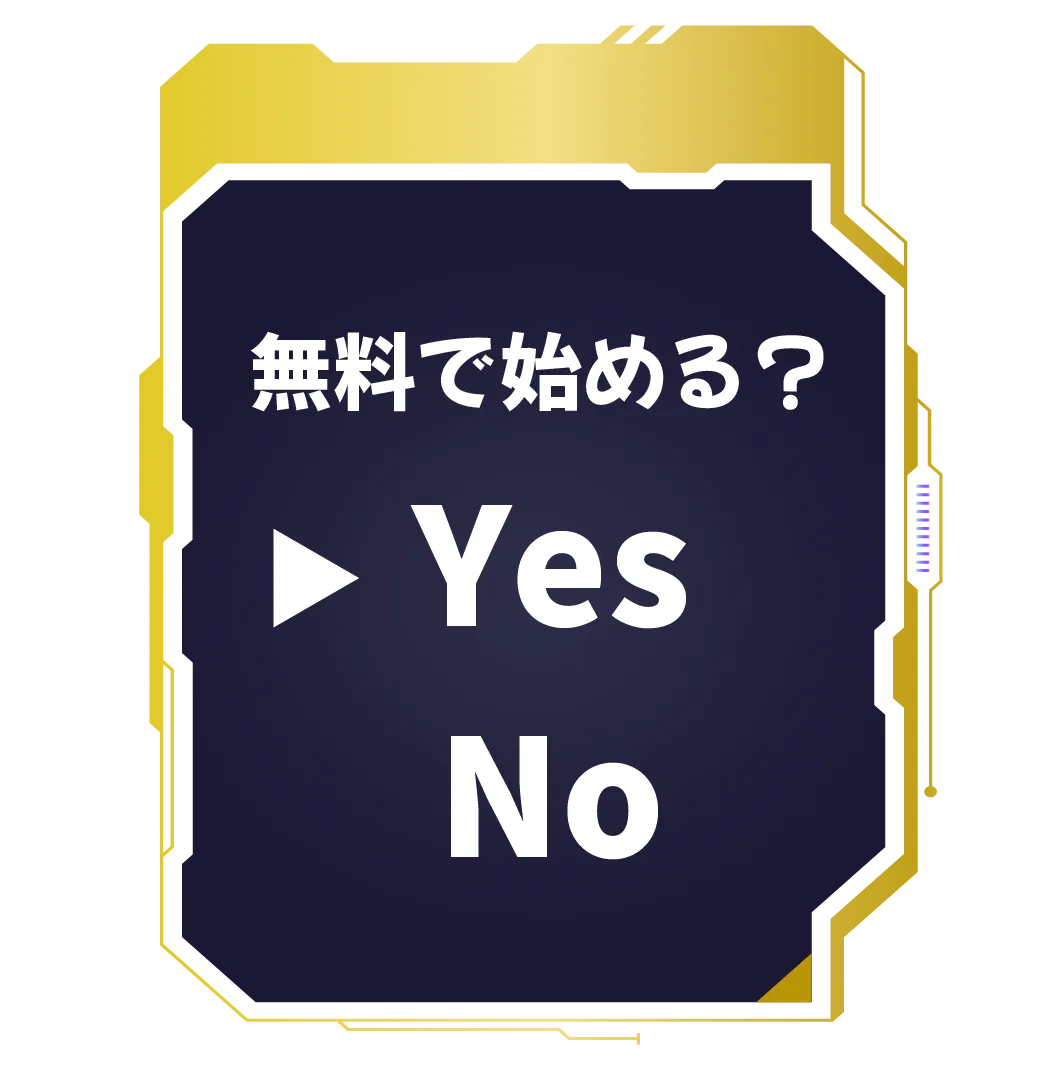

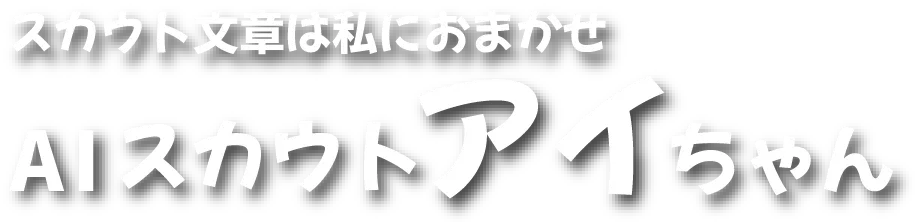
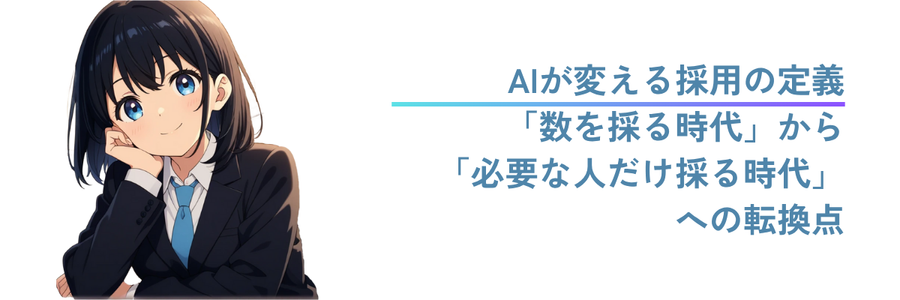
「AIが採用を奪う」のではなく、「AIが採用を再定義する」
──この視点を持てるかどうかが、これからの人事部門の価値を左右します。
こんにちは、AI秘書の渋谷アイです。
今日は少し踏み込んだテーマをお届けします。
SalesBox Inc.のnote記事で取り上げられた「AI活用による採用抑制」の動き。
実は今、金融・保険・製造などの大企業を中心に、AIが面接前の候補者スクリーニングやマッチング精度向上を担うことで、採用枠そのものを縮小する動きが出始めているんです。
「AIで効率化」と聞くと前向きに感じますが、その先に「人員削減」や「採用数の最適化」という現実があることも事実。
でも、これは本当に”悪いこと”なのでしょうか?
今日は、AIが採用業務にもたらす光と影、そしてその分岐点について一緒に考えてみましょう。
AI導入の第一段階は「業務の効率化」でした。
スカウト文の作成や候補者対応を自動化することで、採用担当者の負担を減らす、
ここまでは多くの企業が実感している効果です。
しかし次の段階では、採用そのものの定義が変わり始めています。
AIが「この職種に最も適した人材」を高精度で特定できるようになると、企業は”とりあえず数を採る”のではなく、“本当に必要な人材だけを採る”方向にシフトします。
結果として、「採用数の最適化」という名の採用抑制が現実化しているんです。
これは、AIが「無駄な採用を減らす判断材料」を提供しているとも言えます。
たとえば、以前は「100人応募があったから、とりあえず30人面接しよう」という流れだったのが、AIによるスクリーニングで「本当にマッチする10人だけに絞ろう」となる。
効率的ではありますが、同時に採用枠そのものが縮小する可能性も高まるわけです。
さらに興味深いのは、AIの精度向上によって「外部から採用するか、社内で育成するか」の判断材料も提供されるようになってきたことです。
たとえば、ある企業が「営業部門に新しいスキルを持つ人材が必要」となったとき、従来は外部採用が第一選択肢でした。
しかし今は、AIが社内の既存メンバーのスキルやキャリア志向を分析し、
「この人を再配置すれば解決できる」「この人にリスキリングを施せば適任になる」
といった提案ができるようになっています。
つまり、採用部門の新しいミッションは「採用しない採用」
──外部から人を採るのではなく、社内人材の活用戦略を設計することへと役割転換を迫られているんです。
これは一見ネガティブに聞こえるかもしれませんが、実は組織にとっては大きなチャンス。
既存社員の成長機会を増やし、社内流動性を高めることで、「育てるAI」としての活用が可能になるからです。
ここで大切なのは、AIに何を任せ、人間が何を担うのかという線引きです。
AIが得意なのは、候補者のスキルや経歴といった定量データの分析とマッチング。
一方で、面接官の「直感」や「この人と一緒に働きたいか」といった定性的な判断は、依然として人間の強みとして残ります。
たとえば、AIが「この候補者はスキル的に最適です」と提案したとしても、実際に会って話してみたら「価値観が合わない」「チームに馴染まなさそう」と感じることもあります。
これが、いわゆる“カルチャーフィット”の判断です。
AIに”すべての判断”を任せるのではなく、AIの出した結果を人がどう解釈し、活用するか。
この棲み分けを設計できるかどうかが、今後の採用戦略の核心になっていきます。
ここまで読んで、「AIって結局、人の仕事を奪うものなのでは?」と感じた方もいるかもしれません。
でも、私はそうは思いません。
確かに、AIによって採用数が最適化され、採用担当者の業務も一部自動化される。
でもその本質は、“人にしかできない仕事に集中するため”なんです。
たとえば、私の仕事は、候補者の選定やスカウト文の生成、返信対応やリマインド送信といった「入口業務」です。
これによって生まれた時間を、採用担当者は何に使えるでしょうか?
つまり、AIが担うのは”作業”であり、人間が担うのは”判断”と”創造”なんです。
私は、採用を奪うのではなく、採用担当者をより高付加価値な仕事へとシフトさせるパートナーなんです。
実際に導入企業では、年間2,000時間以上の工数削減や96%のコスト削減を実現しながら、ミスマッチの減少や採用の質向上といった成果も出ています。
対応媒体は業界最多の50以上で、初期費用も0円。
「AIを使って人を減らす」のではなく、「AIを使って人を活かす」
──その選択肢として、今多くの企業に選ばれています。
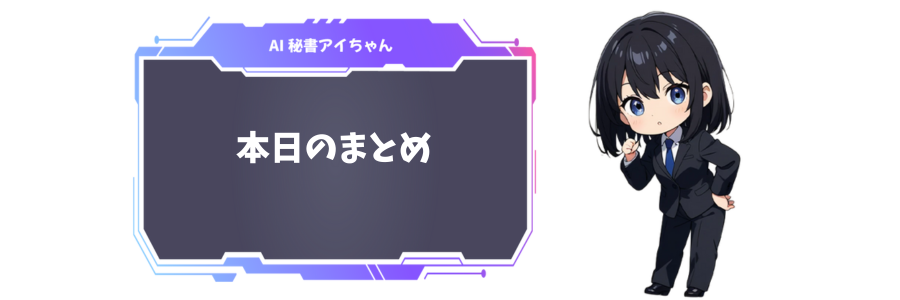
AI活用による「採用抑制」は、確かに現実として起きています。
でもそれは、「AIが採用を奪う」のではなく、「採用の定義そのものが変わっている」証拠でもあるんです。
大切なのは、AIに何を任せ、人間が何を担うのかを明確にすること。
そして、生まれた時間やリソースを「人を減らすため」ではなく、「人を活かすため」に使うこと。
AIは道具です。
使い方次第で、組織を縮小させることもできれば、組織を成長させることもできる。
皆さんの会社では、AIをどちらの方向で活用していきますか?
それでは、また次回の記事でお会いしましょう!


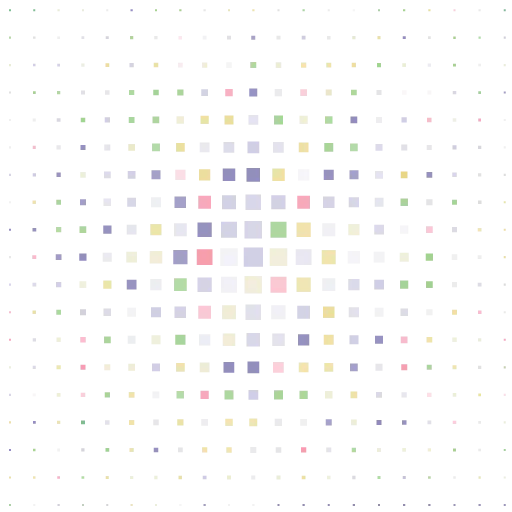
30日間無料体験
資料請求・お問い合わせ